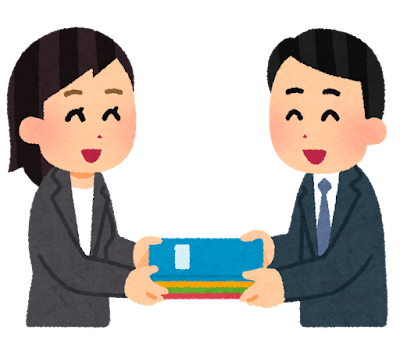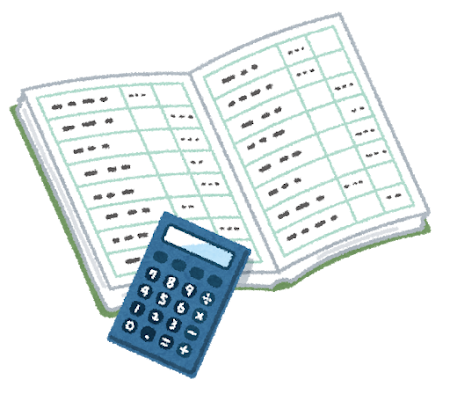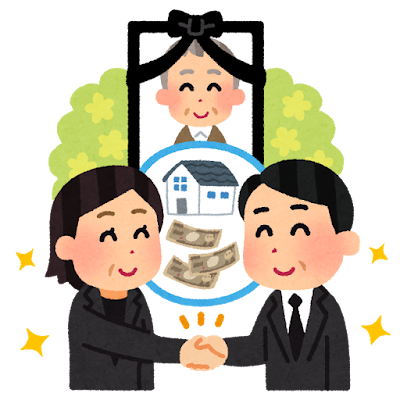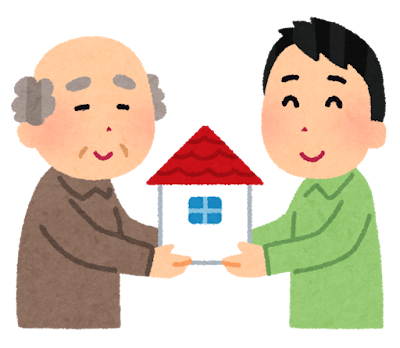・社長一人で運営する法人、従業員を雇う予定のない個人事業主向けの特別料金プランです。
従業員、ご本人以外の役員に給与の支払いが発生した月から基本プランの料金となります。
・日常の税務相談、記帳代行から決算申告までトータルサポートいたします。
プラン料金には、消費税申告料、償却資産税申告料、年末調整料、法定調書作成料、納税代行料が含まれており、年次の決算料を別途請求することはございません。
・年に2、3回ほど、領収書、請求書、預金通帳などの資料が揃ったタイミングでこちらの事務所にお越しいただき、前回までにお預かりした資料に基づき月次業績報告を行います。(ご希望の場合はこちらからの訪問も可能です。)
税務相談は随時対応いたしますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
・ご契約いただいた日の翌月から月額料金が発生します。
初年度のみ着手金として「期首から契約日の属する月までの月額料金の累計額の半額」を、初回の月額料金と一緒に請求させていただきます。
・日常の税務相談、記帳代行から決算申告までトータルサポートいたします。
プラン料金には、消費税申告料、償却資産税申告料、年末調整料、法定調書作成料、納税代行料が含まれており、年次の決算料を別途請求することはございません。
・毎月一定の日に、領収書、請求書、預金通帳、給与明細書などの資料をお持ちいただき、前回までお預かりした資料に基づき月次業績報告を行います。(ご希望の場合はこちらからの訪問も可能です。)
税務相談は随時対応いたしますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
・ご契約いただいた日の翌月から月額料金が発生します。
初年度のみ着手金として「期首から契約日の属する月までの月額料金の累計額の半額」を、初回の月額料金と一緒に請求させていただきます。
・パソコンをご利用のお客様は、資料の受け渡しを専用のクラウドサービスで行うことができます。
・当事務所では、MJS(ミロク情報サービス)の「かんたんクラウド」を導入しており、ご希望のお客様は導入費用を当事務所で負担いたします。
また、当サービスをご利用のうえ、月次業績報告をメール・電話にてご希望のお客様は、各プラン料金から月額3,000円値引きさせていただきます。
・2024年施行の改正電子帳簿保存法により、電子データで受け取った請求書や領収書などの資料は、電子データのまま保存することが義務化されました。
導入後のサポートにつきましても丁寧に説明させていたきますので、是非この機会にご利用ください。
・お客様のご要望を伺い、こちらで用意したフォームに、勤務時間や給与の金額などをご入力いただく方法になります。(源泉所得税、社会保険料などの各控除項目はこちらで計算します。)
・5人を超える場合、1人につき毎月1,000円が基本料金(9,000円)に加算されます。
・従業員情報の登録、給与明細書の作成、源泉所得税の納付代行まで承ります。
専用アプリの導入により、給与明細書は直接スマートフォンなどで参照できます。
・提携振込サービスをお申し込みいただくことにより、振込代行も可能です。
初期費用、月額利用料は無料で、振込手数料も一般的な銀行振込手数料より割安ですので、是非ご検討ください。
・賃金規程・就業規則などの作成、労務管理、社会保険・雇用保険などの事務手続きは、ご自身で行われるか、別途社会保険労務士にご依頼いただくことになります。(ご希望の場合は、社会保険労務士の紹介も可能です。)
・仕訳数は、1ヶ月の領収書の枚数、預金通帳・クレジットカード明細などの行数でおおよその数を見積もることが可能です。
・1期目は無料です。2期目以降は決算終了時の1年間の実績に基づき、今後1年間の毎月の加算料金を提示させていただきます。
・加算料金は、月換算で50仕訳まで無料。50仕訳を超える場合は、100仕訳まで5,000円、150仕訳まで10,000円、200仕訳まで15,000円が毎月のプラン料金に加算されます。
月換算で200仕訳を超える場合は、別途相談のうえ料金を提示させていただきます。
・個人事業主以外の確定申告をスポットで承ります。
・給与の収入金額が2,000万円を超える方や、給与収入があり、その他に副業など、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方は確定申告をする必要があります。
また、以下の場合は確定申告をすれば所得税が還付される可能性があります。
① 総合課税の配当所得や原稿料収入などがある場合
② 給与所得者で、医療費控除・寄付金控除(ふるさと納税等)・住宅ローン控除などを受ける場合
③ 公的年金等の雑所得のみの方で、生命保険料控除・医療費控除・寄付金控除などを受ける場合
④ 給与所得について年末調整を受けていないものがある場合
⑤ 退職所得がある場合
・不動産などを売却した方で、譲渡価額から取得費・譲渡費用を差し引いて計算した結果、譲渡所得(利益)がある方は原則として確定申告が必要です。
また、「マイホームを売却した場合の特別控除の特例」など、各種特例の適用を受ける場合は、譲渡所得(利益)の有無にかかわらず申告が必要です。
・料金表の金額には、不動産の名義変更手続きなど、別途お客様から司法書士にご依頼いただく費用は含まれておりません。(ご希望の場合は、司法書士の紹介も可能です。)
・どのような場合に申告が必要か?
亡くなられた方(以下「被相続人」)の遺産を無償かつ無条件で取得することを相続といいます。
被相続人の遺産総額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、通常は相続税額が発生しますので申告が必要です。
「遺産に係る基礎控除額」とは、3,000万円に600万円×「法定相続人の数」を加算した金額です。
「法定相続人の数」は、オーソドックスな形だと、被相続人に配偶者と子供が二人いた場合は3人で、この場合の「遺産に係る基礎控除額」は、3000万円+600万円×3人=4,800万円になります。
また、遺産の価額は、原則として被相続人が亡くなられた日(以下「相続開始日」)の時価で評価し、そこから住宅ローンや葬式費用などの金額をマイナスして、遺産総額を計算します。
なお、相続に関するお話でよく耳にする「配偶者に対する相続税額の軽減」や「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合は、税額の有無にかかわらず必ず申告が必要です。
・具体的にどのような手順で進めるのか?
相続が発生した場合、おおまかな流れとして、以下のような手順で手続きします。(期限があるものもあり注意が必要です。)
① 病院や医師から死亡診断書を取得
② 相続開始日から7日以内に、被相続人の住所地の市区町村に死亡届を提出
③ 健康保険証の返還、未支給の年金や生命保険金などの請求(国民健康保険、国民年金の場合は相続開始日から14日以内に届け出ます。)
④ 被相続人や相続人と予想される者全員の戸除籍謄本などを取り寄せて、法定相続人が誰なのかを特定
⑤ 遺言書の有無を確認し、検認(遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防止するための手続きです。公正証書による遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要です。)が必要な場合は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申立て
⑥ 被相続人の財産(預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、生前の贈与など)と債務(住宅ローンなどの借入金、税金・医療費などの未払金、葬式費用など)をおおまかに把握し、相続税の申告が必要になりそうか確認(遺産総額が「遺産に係る基礎控除額」を超えそうか確認します。)
⑦ 相続の放棄をする相続人がいる場合、限定承認(相続する財産の範囲内で債務を引き継ぐこと)をする場合は、相続開始日から3ヶ月以内に被相続人の住所地の家庭裁判所に申立て
⑧ 相続開始日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に、亡くなられた年の1月1日から相続開始日までの所得税の申告・納付(準確定申告といい、納税額は被相続人の債務として遺産総額から控除できます。)
⑨ 被相続人の財産と債務に関係する資料を全て取り寄せて、財産評価を行い正確に集計
⑩ どのように相続するかを共同相続人全員で協議して、遺産分割協議書を作成(遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容で相続します。)
⑪ 相続開始日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に相続税の申告・納付
⑫ 相続財産・債務の名義変更手続き(不動産は相続した日から3年以内に登記が必要です。)
・料金表の金額には、不動産の名義変更手続きなど、別途お客様から司法書士にご依頼いただく費用は含まれておりません。(ご希望の場合は、司法書士の紹介も可能です。)
・贈与とは、無償で財産権を移転する契約であり、当事者の一方(以下「贈与者」)が、ある財産を無償で相手方(以下「受贈者」)に与える意思を表示し、受贈者が受諾をすることによってその効力が生じます。
受贈者が、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計が110万円を超える場合、通常は贈与税が発生するので申告が必要です。
贈与財産は、原則として贈与を受けた日の時価で評価し、贈与を受けた側の受贈者が申告します。
贈与税の計算方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法があり、それぞれ以下のような特徴があります。
いずれも1月1日から12月31日までの暦年単位で計算して、翌年2月1日から3月15日までの間に申告・納税します。
通常は「暦年課税」で計算しますが、届出書の提出により「相続時精算課税」を選択することも可能です。
1.暦年課税
(1)計算方法
① その年分の贈与財産の価額の合計額 - 基礎控除額(110万円)= 差引残額(千円未満切捨)
② ① × 税率(10%~55%)- 速算表による控除額 = 贈与税額(百円未満切捨)
(2)相続発生時の手続き
元々は相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価額が、「生前贈与加算」として相続税の計算上持ち戻しの対象となっていましたが、2024年1月1日以後に贈与を受けた財産については、相続開始前7年以内に遡って持ち戻しの対象とする改正が行われました。(相続開始前3年以内よりも前に贈与を受けた財産については、その合計額から100万円を控除できます。)
なお、「生前贈与加算」する金額は基礎控除額(110万円)を差し引く前の金額です。
また、「生前贈与加算」の対象となった財産につき課せられた贈与税額は、相続税額から控除できます。
2.相続時精算課税
(1)計算方法
贈与の年の1月1日において60歳以上の贈与者から、同日において18歳以上の子や孫へ贈与する場合、届出書の提出により「相続時精算課税」を選択することができます。
受贈者が、贈与者の異なるごとに届出書を提出し、贈与者ごとに以下の方法で贈与税額を計算します。
なお、「相続時精算課税」の基礎控除額は、複数の贈与者から贈与を受けた場合、1年間の合計額が受贈者単位で110万円までとなり、贈与財産の価額で贈与者ごとに按分します。
また、「相続時精算課税」を選択後は、撤回することができないため注意が必要です。
① その年分の贈与財産の価額の合計額 - 基礎控除額(110万円)- 特別控除額(贈与者ごとの各年の累計額で2,500万円まで)= 差引残額(千円未満切捨)
② ① × 20% = 贈与税額(百円未満切捨)
(2)相続発生時の手続き
元々は「相続時精算課税」により贈与を受けた場合、適用財産のすべての価額が、相続税の計算上持ち戻しの対象となっていましたが、改正により、2024年1月1日以後に贈与を受けた財産については、各年ごとに基礎控除額の110万円までの金額は持ち戻しの対象から除外されました。
また、「相続時精算課税」の適用財産につき課せられた贈与税額は、相続税額から控除することができ、控除しきれなかった金額があるときは還付されます。
・料金表の金額には、不動産の名義変更手続きなど、別途お客様から司法書士にご依頼いただく費用は含まれておりません。(ご希望の場合は、司法書士の紹介も可能です。)
税務調査に関する税理士報酬は、事前準備や調査立会日にかかる日当が、一日あたり3万円から5万円程度、修正申告料金は、修正対象となる年数に応じて数十万円になることが一般的です。
しかし、当事務所が対象とする比較的小規模な事業者の皆様にとっては、これらの費用が資金面で大きな負担となるうえ、調査期間中の営業活動への支障や追加納税額の発生も避けられない場合があります。
当事務所では、このようなご事情を考慮し、こちらで作業を承った日以降に発生した要因に基づく税務調査については、事前準備や調査立会日の日当、調査後の修正申告料金などをすべて無料で承っております。
ただし、以下の場合は別途ご相談のうえ、適正な料金を提示させていただきます。
・税務調査の目的が、当事務所で作業を承った日以前の要因に基づいている場合
・当事務所では把握できない要因に基づく場合
・調査結果に基づき、不服申し立て等の手続きを希望される場合